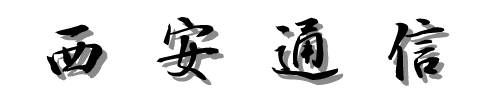 |
|
|
|
|
|
第2回 「気」とはどんなもの? |
|
|
|
|
|
「気」は目に見えない生命エネルギー 中国医学における「気」とは、私たちの身体を流れる目に見えない生命エネルギーを意味します。ただしこれはあくまでも概念であって、量はどの位なのか、何色なのか等は追求しません。日本人には理解しにくいものですが、中国医学では基本中の基本です。「気」は「血」とペアになっています。「気」がうまく流れれば「血」もスムーズに流れます。逆に「気」が詰まると「血」も詰まります。いわゆるうっ血状態になるのです。このように「気」は血液の循環と密接な関係があるばかりでなく、各臓腑を正常に活動させたり、新陳代謝にも大きく作用します。例えば「気」が弱いと老廃物を排出する力が弱まります。反対に、とどめておく力が弱まることもあります。慢性の下痢や便秘、トイレがやけに近い人がそうです。 「気」は臓腑で作られる 「気」は大きく三つに分けられます。 「気」と整体・鍼灸治療 内科の治療に何故整体や鍼灸が使われるのでしょうか?「ツボ」を強く刺激することによって、「気」の流れと臓腑の働きを良くすることが出来るからです。自分自身の治癒力が高まり、自然に体調が良くなってきます。しかし残念ながら「気」は損失しやすいものなのです。栄養不足や体力消耗(重労働、出産、遊び過ぎ等)、外気からの風邪、ストレス等の原因で、「気」のバランスは崩れてしまいます。健康診断では正常なのに次のような症状が表れる方は、「気」に問題があると考えてよいでしょう。→手足のだるさ、不眠、おなかの腫れ、げっぷ、下痢、胃痛、ぎっくり腰等。 「気」を補う漢方薬 人参(にんじん)・党参(とうさん)・黄氏(こうし)・白術(しろじゅつ)・山芋(やまいも)・ナツメ(なつめ) |
|