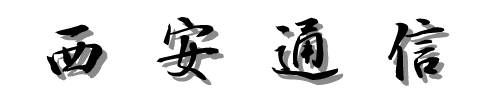 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
第14回 腰痛について その二 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
腰痛に伴ういろいろな症状 中医学では腰痛を単に腰の病気とはせず、痛みは「反応」としてとらえます。
* 部位は西安通信No13の図をご覧下さい。 中医学における腰痛の治療法 上記の表はおおまかに分けたもので、一人一人の原因はすべて異なります。患者さんからの「腰痛」という自己申告だけで診断することは出来ません。慢性か急性か、先天性か後天性か、発病の時期、他の症状などを基に中医学独自の診断によって原因を解明し、患者さんに合った治療法を行います。腰痛の治療に来たのに何故お腹をグリグリ押されるのだろう?何故頭にまで鍼を刺すのだろう?と疑問に思われるかもしれませんが、これらはすべて痛みの原因を治療しているのです。腰だけのマッサージでは気持ち良くても治療になりません。表面の症状改善だけでなく、元の原因を治療することが中医学の基本概念であり、腰痛に限らずあらゆる病気に該当されます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||